第5回 プロセスの視点 〜内部業務プロセスの「見える化」と「評価」のためのフレームワーク〜:【連載】コミュニケーションデザインのための戦略フレームワーク(2/2 ページ)
内部業務プロセスの「見える化」と評価方法
内部業務プロセスを「見える化」することは誰にでもできそうですが、意外に行き詰まったり、悩んでしまい時間がかかってしまうものです。時間がかかるのはよいとしても、せっかく「見える化」したものが役に立たなかったり、やり直しになってしまうケースも少なくありません。しかし、フレームワークを使うことで、その問題を簡単に解決することができます。
業務手続きを「見える化」するうえで、いきなり業務手続きを描いたのでは、業務の粒度が合わなかったり、業務のヌケやモレがあったり、あるいは、不必要に複雑な手続きとなってしまう危険性があります。そこでポイントとなるのが段階を経たプロセスモデリングです。内部業務プロセスは、戦略目標を起点に、「サービス」から「プロセス」、そして「業務」へと段階的に落としていく(モデリングを進めていく)ことがポイントです。
サービスとは
サービスとは戦略目標を達成するために、それに関わる組織とその組織が担う活動の総称です。
例えば、戦略目標「(2)新しいお客さまを開拓する(アクイジション)」を実現するために、マーケティング部門やセールス部門が担う次のような活動が「サービス」です。
- 見込み客を獲得するための活動(Lead Generation)
- 見込み客を育成するための活動(Lead Nurturing)
- 営業活動(Sales)
サービス構成の「見える化」を図るメタプロセス
そのサービスの関係を「見える化」し、活動の価値の連鎖を捉えたモデルが「メタプロセス」です。
例えば、先の「(2)新しいお客さまを開拓する(アクイジション)」活動の価値の連鎖は次のようになります。それぞれのサービスが連鎖され、成果として新規顧客が開拓されるわけです。
業務構造の「見える化」を図るビジネスプロセス
サービスモデルは、部門が担う活動を一般化(汎化)し、その活動の連鎖を描いたモデルです。実際の活動を考えた場合、具体的な施策(手段)に応じてサービスモデルは具象化されることになります。
例えば、先の「サービスモデル(アクイジション)」は、広告やテレビCM、展示会など、さまざまな手段をとることができます。そして、サービスモデルはある手段に特化した価値の連鎖として描き直されることになります。その具体化、もしくは分解された活動が、「アクティビティ」です。そして、そのアクティビティの「仕組み」や「関連(因果関係や依存関係)」を「見える化」したモデルがビジネスプロセスです。
一般的に、ビジネスプロセスをモデリングするために、IDEF0と呼ばれる規格が活用されます。IDEF0は、別名「機能モデリング」とも呼ばれており、業務活動をアクティビティというレベルに分割し、それぞれのアクティビティに対しインプットとアウトプット、制約と機構という4つの情報(ICOM)を定義する手法です。
それでは、先の「サービスモデル(アクイジション)」を「展示会」に当てはめ、そのビジネスプロセスを「見える化」してみましょう。
関連記事
 第1回 生活者の“買いたい”気分を創り上げるマーケティングコミュニケーション
第1回 生活者の“買いたい”気分を創り上げるマーケティングコミュニケーション
企業は「売る視点」に立ってメッセージを発信する。生活者は「買う視点」から企業のメッセージを受信する。企業と生活者のコミュニケーションは理想的な形で成立しているのだろうか? そもそもマーケティングコミュニケーションの理想的な形とは? シナジーマーケティングの工藤浩志氏によるコミュニケーションデザインのための新連載。 第2回 コミュニケーション戦略マップ――BSC各視点の因果関係を整理
第2回 コミュニケーション戦略マップ――BSC各視点の因果関係を整理
今回はコミュニケーション戦略マップの概要を紹介します。コミュニケーション戦略のビジョンや目的、達成目標を俯瞰的に捉え、さらには、それらを組織で共有し、共鳴して増幅できる環境を整えるための指針です。 第3回 財務の視点 〜コミュニケーション戦略目標の“見える化”〜
第3回 財務の視点 〜コミュニケーション戦略目標の“見える化”〜
コミュニケーション戦略目標について「いかに会社を存続させるのか」を起点に検討しましょう。事業存続には2つの達成目標があります。「財務力」と「企業の社会的責任(CSR)」です。今回は「財務力」に的を絞り、コミュニケーション戦略目標の組み立て方を解説します。 第4回 顧客の視点 〜顧客資産価値の「見える化」と顧客セグメンテーションのためのフレームワーク〜
第4回 顧客の視点 〜顧客資産価値の「見える化」と顧客セグメンテーションのためのフレームワーク〜
ビジネスを維持および成長させるための源泉は「お客さま」が握っています。今回は「お客さま」に的を絞り、過去/現在/未来において、お客さまが企業にもたらす価値を「見える化」する方法と、お客さまの特性や特徴を知るための「切り口」を紹介します。 第5回 プロセスの視点 〜内部業務プロセスの「見える化」と「評価」のためのフレームワーク〜
第5回 プロセスの視点 〜内部業務プロセスの「見える化」と「評価」のためのフレームワーク〜
今回お話しするマーケティングコミュニケーション活動におけるプロセスの視点では、「内部業務プロセス」と「コミュニケーションデザイン」という2つのケーパビリティを高めるためのフレームワークやモデル、モデリングの進め方、そしてモデリングを進める上でのポイントやコツを紹介します。 第6回 プロセスの視点 〜お客さまの心を動かすコミュニケーションデザインのためのフレームワーク〜
第6回 プロセスの視点 〜お客さまの心を動かすコミュニケーションデザインのためのフレームワーク〜
今回お話しするマーケティングコミュニケーション活動におけるプロセスの視点では、お客さまの心を動かすコミュニケーションデザインのケーパビリティを高めるためのフレームワークやコミュニケーションデザインの進め方、そして進める上でのポイントやコツを紹介します。 第7回 学習と成長の視点 〜お客さま経験価値が導くお客さまへの最適な提案、お客さま経験価値マネジメントのためのフレームワーク〜
第7回 学習と成長の視点 〜お客さま経験価値が導くお客さまへの最適な提案、お客さま経験価値マネジメントのためのフレームワーク〜
今回お話しするマーケティングコミュニケーション活動における「学習と成長の視点」では、財務の視点や顧客の視点、そして業務プロセスの視点で得られた戦略目標やターゲット、コミュニケーション戦略ストーリーの達成度を「見える化」するためのフレームワークを紹介します。 第1回 衰退する企業と躍進する企業、違いは「事業定義の仕方」にある
第1回 衰退する企業と躍進する企業、違いは「事業定義の仕方」にある
「製品志向」で事業を定義する企業は時代の流れに取り残される。米国の鉄道会社のように――。日本アイ・ビー・エム 永井孝尚氏によるマーケティング原論の第1回。 第2回 「多機能/高品質なのに低収益」――間違いだらけの顧客中心主義から抜け出す
第2回 「多機能/高品質なのに低収益」――間違いだらけの顧客中心主義から抜け出す
ターゲット顧客が必要としていなければ、あえてその要素は切り捨てること。そうしなければ、どの会社も同じような商品を作り、多機能/高品質、かつ低収益な商品を数多く生み出し続けることになる。 第1回 CMOが日本の組織に馴染まない理由
第1回 CMOが日本の組織に馴染まない理由
CMOとは何者か? マーケティングドリブン型組織が持ち得る力とは? マーケティングを軸に組織再編を考える松風里栄子氏の新連載。第1回はマーケティング部門が見直される背景および企業の構造再編を阻む要因を整理する。 第2回 グローバル企業のマーケティング組織マネジメント
第2回 グローバル企業のマーケティング組織マネジメント
グローバル企業はどのようなマーケティングマネジメントを志向し、チャレンジし、実践しているのか。3人のグローバルCMOへのインタビューを通じて、その要点と課題を考察する。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
関連メディア
アクセストップ10
- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと
- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに
- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大
- 広告運用担当者が押さえるべき「数字の考え方」 3つのポイントとは
- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない
- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦
- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ
- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由
- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力
- 「マーケター通信」サービス終了のお知らせ
CX Experts アクセストップ10
- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由
- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX
- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは
- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心
- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体
- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?
- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ
- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由
- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている
- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ
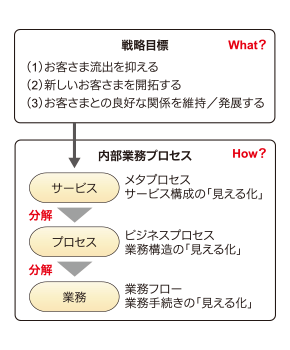 戦略目標と内部業務プロセスの関係
戦略目標と内部業務プロセスの関係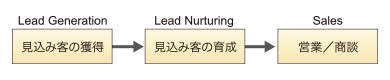 サービスモデル(アクイジション)
サービスモデル(アクイジション)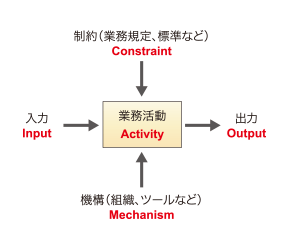 IDEF0表記法
IDEF0表記法







