業界トップランナーが語る「イベントDX」 リアルもオンラインも、もっと変われる:データ活用でイベントの効果を最大化する方法とは?
コロナ禍を経て、イベントの在り方は大きく変わった。データを駆使してイベントの体験価値を最大化するために何をすればいいのか。イベントDXに関わるエキスパートたちが語り合った。
企業イベントはコロナ禍を経て変革期にある。オンラインイベントは単なるリアルの代替的な選択肢ではなくなっているし、リアルのイベントがデジタルと無縁でいいはずもない。
オンラインかリアルかは手段の話にすぎない。本質は参加者の体験価値を最大化して顧客エンゲージメントを向上させることにある。そして、そのための鍵となるのがデータだ。
ブイキューブが2024年8月2日に開催したイベント運営者のためのイベント「V-CUBE EVENT SUMMIT 2024」には、イベントDXに挑む業界のトップランナーが集い、イベント参加者データの分析を通じてインサイトを得る方法や効果的なエンゲージメント戦略、参加者の行動変容を引き起こすための取り組みなどを語った。
本稿では「データがイベントの成功をアップデートするーリアルとオンラインの改善戦略」と題したパネルディスカッションのハイライト部分を紹介する。
イベントのデータ活用、最前線は? 参加者の「表情分析」も
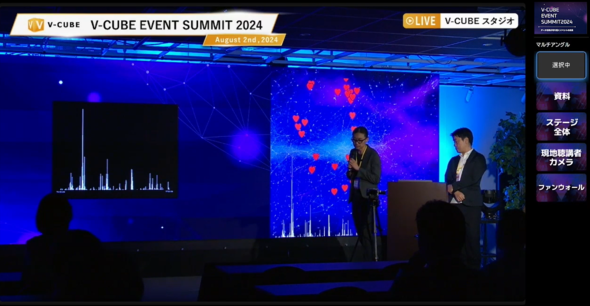 リアルとオンラインのハイブリッドで開催された「V-CUBE EVENT SUMMIT 2024」では、独自の映像技術を用いた演出に加え、エモーショナルスタンプの活用など、参加者の感情を可視化する手法、イベント参加後のブランド認知・好感度変化の測定調査など、イベントに関連した最新テクノロジーが用いられた。
リアルとオンラインのハイブリッドで開催された「V-CUBE EVENT SUMMIT 2024」では、独自の映像技術を用いた演出に加え、エモーショナルスタンプの活用など、参加者の感情を可視化する手法、イベント参加後のブランド認知・好感度変化の測定調査など、イベントに関連した最新テクノロジーが用いられた。登壇者は、イベントプラットフォーム「eventos」を提供するbravesoftの菅澤英司氏、博報堂プロダクツ イベント・スペースプロモーション事業本部エグゼクティブ・エクスペリエンスプロデューサーの中島康博氏、イベントを主催したブイキューブのイベントDX事業戦略室室長兼営業本部副本部長の菊地類氏とグループイノベーション室CDOの花輪俊行氏。JTBコミュニケーションデザインでイベントプロデューサー/イベンテックエバンジェリストを務める吉井和人氏がモデレーターを務めた。
冒頭、「イベントをただオンライン化できればよかった3年前と異なり、参加者の行動・態度変容が求められるようになった。そのためにデータによる管理が重要になっている」と語ったのは、今回のイベントを企画した菊地氏だ。
イベントの効果を改善するには、そもそもそのイベントがどれだけ参加者の心に働きかけたのか、きちんと効果測定ができていることが大前提となる。
従来、リアルのイベントの効果測定といえば会場アンケート調査一択だった。しかし、来場者の満足度は開催場所や開催のタイミングによっても左右される。また、アンケートに答える時間が十分に取れないなど、評価方法として不十分だ。そこで博報堂プロダクツは2019年より、イベント開催の前後で同一人物へのアンケートを実施して、その比較によりリアルな態度変容を測定してきた。ただし、この方法はコストがかかる上、来場予約者と実来場者の紐づけが難しいなど課題もあった。しかし、オンラインイベントであればこの課題は簡単にクリアできる。そこで、ブイキューブと共同で「オンラインイベント版ブランドリフト調査(仮称)」を開発した。これにより、オンラインイベントを通じて「認知」「好意度」「購入意向」「ブランドイメージ」がどのように変化したかが分かる。また、画面デザイン(LP、プログラム、画面遷移)や映像演出とそれらの指標の相関も把握できるようになる。
ブランドリフトというとB2C向けのような印象だが、中島氏は「何かしらの商材やサービスでビジネスしているのはB2CでもB2Bでも同じ。認知、興味、購入意向のそれぞれの項目における質問項目の作り方を工夫することで、B2Bでも十分に有効な調査ができる」と話した。
イベント業界の関係者であれば誰もが気になるのが参加者の反応だ。続けて話題になったのは、それを測定可能なテクノロジーである「表情分析」についてだ。ビジネスイベントなど固い内容では、そもそも参加者の感情が大きく動くことはない。そこでブイキューブでは表情の「絶対値」ではなく「変化」に着目していると花輪氏は説明する。例えば、イベントの中である話に触れたときに無表情だった参加者の顔がパッと明るくなったというような変化である。表情の変化データの活用例としては、イベントの文字起こしデータの中で、人の表情が変わった箇所を明確にし、そこを中心にイベントレポートをまとめるといった用途が考えられるという。
イベントDXを推進し、イベントマーケティングに特化した日本最大級の動画メディア「イベ博」を運営するbravesoftの菅澤氏はオフラインでのデータ活用の可能性について問われ「具体的に様々なデータが集まっている。リアルとオンラインを組み合わせて定量的なデータがこれからどんどん明らかになっていくと思う」とコメントした。
参加者が「いいね」を押したら話し手の行動が変わるような仕組みも
今回のパネルディスカッションの題名にあるように「データがイベントの成功をアップデートする」というと、どうしても主催者側がデータをどう取得して活用するかという話になりがちだ。しかし、逆にイベントの参加者がデータを活用するという視点もあるはずだ。吉井氏は、「参加者にアンケートに答えてもらったり、『いいね』を押してもらったりしたら、そのデータを基にリアルタイムで話し手のアクションが変わるような仕組みがあってもいいのではないか」と問いかけた。例えば、話し手が「今の話題に対するいいねが多いので、もう少し具体的にお話ししましょう」と本来の予定にはない話を掘り下げて話すといったことだ。参加者が「私がいいねを押すと、何をしてもらえるのか」が分かる仕組みで、「参加者にとってのデータ活用」ともいえる。
この問いに対して菊地氏は「イベント主催側として重要なのは、参加者のアクションをきちんと拾ってあげるオペレーションをすること」と話した。花輪氏も「イベントのプラットフォームを提供する側からすれば、参加者の『うなずき』のように無意識に出てしまう行動をきちんと拾い、参加者の潜在的な興味・関心を見える化が大切。見える化できれば、その興味・関心をさらに高めるためのアプロ―チを考えられる」と方向性を示した。
企画・制作と演出・運営の両方がそろってこそ行動変容が生まれる
イベント主催者が参加者の行動変容を起こさせるためにまず重視すべきこととして中島氏は「企画段階でどういう変化を起こしたいのかをしっかり考え、ストーリーを作ることをまずは重視している」と説明した。ストーリーの中で設定した目標に対し、そこに到達するまでのプロセスを設計し、イベントを作り込んでいくということだ。ただし、それだけでは不十分であると付け加えた。
「参加者が想定通りに反応し、行動するとは限らない。行動変容を起こさせるには、実際のイベントでの演出と運営が重要。参加者をしっかりと誘導して行動変容を起こさせる。企画・制作がきちんとできて50%、イベントの演出と運営ができて50%。両方ができて初めて行動変容の可能性が見えてくる」(中島氏)
イベントは「箱」を作るだけでは成功しない。行動変容を促すには、まず現状を正確に把握することが重要だ。花輪氏は「参加者が無意識に示す興味や関心を可視化することが鍵になる。これにより、どうすればそれを引き出せるか、具体的なアプローチを取ることが可能になる」と語った。
データを取得し、活用する仕組みが整いつつある現在、イベントを「やりっぱなし」にせず、継続的に改善していく姿勢が求められている。こうした取り組みを積み重ねることで、イベントはより高い成果を生み出し、さらなる価値を生み出すことができるだろう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
関連メディア
アクセストップ10
- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと
- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由
- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力
- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない
- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに
- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦
- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ
- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大
- AIは“ググる”を終わらせる? Google検索の大変革期に何をすべきか
- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年5月)
CX Experts アクセストップ10
- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由
- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは
- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX
- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心
- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体
- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?
- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ
- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由
- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている
- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ








