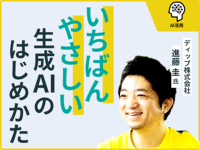データの有効活用には「仕組みと組織」をこう変えろ Webサイトで結果を出すためのPDCAサイクル実践方法(後編):小川卓の「学び直しWebサイト改善」(2/2 ページ)
WebマーケティングでPDCAサイクルは非常に重要です。ただ、PDCAサイクルはあくまでも仕組みです。仕組みを実行するには人や組織、文化も必要になります。
データドリブンで継続的にPDCAサイクルを回すために押さえるべき組織体制
どの部分を社内で担うのか、どの部分を社外と連携するのかは会社規模、予算などによって変わるので、必ずしも正解はありません。
ですが、これまでの私の経験値から整理すると、効果的なデータドリブンなPDCAサイクルを実現するためには、以下の職種と役割が必要ではと考えています。
必要な職種と役割
それぞれ明確に必要なスキルが違うため、適切な人材がいるかを確認し、社内からの登用や今後の採用などの検討に役立ててください。
ディレクター
- 全体のゴールやKPIを基にした優先順位付け
- ブランド部署との調整力と情報収集力
- 施策実行のための予算管理や技術導入、各人員のサポート
- マーケ会社との連動
アナリスト
- どのような情報を収集すべきかの設計
- 必要な情報を集めるための施策やツールの検討
- エンジニアと連携しながら、データ取得や分析環境の構築
- 定期的なレポート作成とそこからの示唆の提示
エンジニア
- アナリストと連携してのデータ設計や取得対応
- デザイナーや企画側と連動し必要な機能の開発やテスト
- 分析や施策実行に利用するツールや機能の最適化
デザイナー
- 企画の情報を分かりやすく制作物への反映させる
- デザイナーの視点からの気付きや施策の提案
- UIの評価をするためのA/Bテストのアイデア出し
- 制作会社に対してのディレクション
企画・プロモ
- 他メンバーからのインプットを基にした企画の立案
- 企画実行のためのブランドチームとの調整や予算確保
- 広告代理店とのコミュニケーションを通じたプロモの実施
「仕組み」を用意するだけでは成果は出ない 最後は「人」
12回にわたった小川卓の「学び直しWebサイト改善」シリーズも今回が最後です。ここまで、Webサイト改善に必要となるさまざまな内容を解説してきました。
データ取得・レポート・分析にも多く触れてきましたが、これらはあくまで手段です。本来の目的は、改善施策を出す・実行する・それらを評価し、また次へとつなげていくことです。
繰り返しにはなりますが、継続的なPDCAサイクルを支えるデータドリブンな文化の定着は、仕組みを用意するだけでは実現できません。最後は「人」なのです。
そのために、経営やマネジメント層には、「理解を示す」「障害を取り除く」、そして「自分が確信を持つまで考えて信じる」ことが求められます。
まずは、データドリブンな改善活動を業務ミッションとして担ってもらう人材を用意し、小さくても一度PDCAサイクルを回すことから始めましょう。積極的に発信してくれるタイプの人材を見つけ、やれる範囲からスタートして成果を出すことで、その人が周りを巻き込み、次の人材が出てくる好循環を作り出せます。
現場の担当者は、「自分の改善指標を明確にする」「PDCAサイクルをより回りやすくする」「自分で解決できない場合は周りや上司に相談する」ようにしましょう。
既存の業務を「捨てる勇気」と新しい業務に「踏み出す勇気」を持って、PDCAサイクルを回せば、今よりもっと成功しやすい組織が出来上がり、今よりもっと働きやすい環境も手に入るでしょう。
このシリーズの学びから何ができるかを考えて、まずは1つチャレンジしてみてください! では、また別の機会にお会いしましょう!
【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2025夏 開催決定!
従業員の生成AI利用率90%超のリアル! いちばんやさしい生成AIのはじめかた
【開催期間】2025年7月9日(水)〜8月6日(水)
【視聴】無料
【視聴方法】こちらより事前登録
【概要】ディップでは、小さく生成AI導入を開始。今では全従業員のうち、月間90%超が利用する月もあるほどに浸透、新たに「AIエージェント」事業も立ち上げました。自社の実体験をもとに、“しくじりポイント”も交えながら「生成AIのいちばんやさしいはじめ方」を紹介します。
執筆者 小川卓
おがわ・たく UNCOVER TRUTH CAO(Chief Analytics Officer)。Webアナリストとしてマイクロソフト、ウェブマネー、リクルート、サイバーエージェント、アマゾンジャパンなどで勤務。解析ツールの導入・運用・教育、ゴール&KPI設計、施策の実施と評価、PDCAをまわすための取り組みなどを担当。全国各地で講演を毎年40回以上行っている。
UNCOVER TRUTHについて
UNCOVER TRUTHは、データ活用基盤であるCDP「Eark」の提供や、それらCDPの構築と活用を支援するコンサルティングサービスと、コンテンツデータによるユーザー体験分析ツールの「Content Analytics」を提供しております。各ソリューションを通じて、企業が保有する1stPartyDataの分析や活用を促進しています。
詳細はこちら→ Content Analyticsサービスサイト
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 Webサイトを改善するなら「比較せよ」 そのワケは?
Webサイトを改善するなら「比較せよ」 そのワケは?
Webサイト改善を進めるときに重要となる「比較する力」について解説します。 「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術
「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術
「SNSのフォロワー数は増えているのに、売り上げへの貢献が見えない」「オンライン施策と店舗集客の関係性が分からない」――。多くの広報・マーケティング担当者が、一度は直撃したことがある課題だろう。そんな中、つけ麺チェーン「三田製麺所」を運営するエムピーキッチンホールディングスは、SNSやWebを活用した認知拡大から、コアファンの育成、そして売り上げ貢献までを可視化する独自のロジックを確立した。 どんなWebサイトでも「必ず最初に分析すべき」5つの項目
どんなWebサイトでも「必ず最初に分析すべき」5つの項目
どのようなWebサイトの分析でも基本は同じ。最初に行うべき5つの項目について解説します。 使いにくいWebサイト、原因は? 必ず確認すべき10項目とは
使いにくいWebサイト、原因は? 必ず確認すべき10項目とは
今回は、Webサイトの課題の見つけ方と仮説の洗い出しからどのような分析を行うのかを解説していきます。 DeNAを支える第2の柱「Pococha」 急成長の背景にある、徹底したユーザー理解
DeNAを支える第2の柱「Pococha」 急成長の背景にある、徹底したユーザー理解
DeNAが提供するライブコミュニケーションアプリ「Pococha」が、同社の収益の柱になりそうだ。急成長の背景には、同サービスが長年ユーザー視点に立ったアプリ運営を強化してきたことがある。Pocochaはこれまでに、どのようなユーザー体験のアップデートを重ねてきたのだろうか。 「ぶっちゃけ面倒くさい」 コンテンツマーケの“難題”を、生成AIで解決する超時短術とは?
「ぶっちゃけ面倒くさい」 コンテンツマーケの“難題”を、生成AIで解決する超時短術とは?
昨今の生成AIブームで、コンテンツマーケティングの在り方が大きく変わっている。AIの力でコンテンツの制作工数が飛躍的に改善し、企業が発信可能となるコンテンツ量は間違いなく増えていくと予想される。この記事では、生成AIを味方にしながら自社のコンテンツ力を高め、営業売り上げの貢献につなげるヒントを解説する。